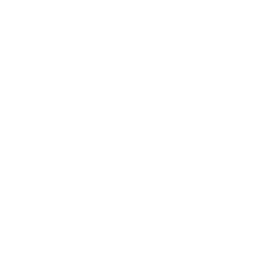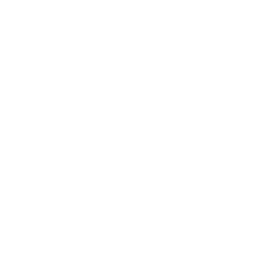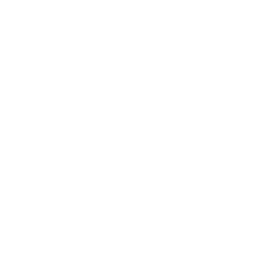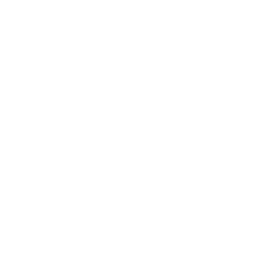食品添加物は安全?!

こんにちは、連日蒸し暑い日が続いていますね、、、、
こんな蒸し暑い日に気になるのが、食中毒!食中毒にかかると辛いですよね。私も一度かかったことがあり、本当に大変だったことを覚えています。さて、そんな食中毒になりやすいこの時期ですが、食中毒にならないよう役立っているものは何だと思いますか?
実は、普段極力摂取したくないと嫌われている製品、食品添加物なのです。
食品添加物と聞くだけで拒否反応示したくなる、、、という方もいらっしゃるかと思います。
実は私もその一人でした、、、、しかし、品質を保つのにはとても重要な働きをしているのです。
と言いながら、私もざっくりとした知識しかないので(笑)
今回は、食品添加物について学んでいきたいと思います♪
食品添加物とは
食品の製造過程において、食品の加工や保存の目的に添加、混和などの方法によって使用するもの、甘味料や調味料、香料、保存料などの製品のことを示しています。
日本での食品添加物は、主に4つの分類に分けられています。
- 指定添加物:安全性と有効性を確認し、厚生労働省が使用してよいと定めた食品添加物。
- 既存食品添加物:長年使用されていた実績をもとに厚生労働省が使用を認めている添加物。
- 天然香料:動植物から得られる天然物質で、食品に香り付けをする目的で使用されるもの。
- 一般飲食添加物:一般に飲食に供されているもので添加物として使用されているもの。
指定添加物
安全性と有効性を確認し、厚生労働省が使用してよいと定めた食品添加物。
例:●甘味料:キシリトールやアスパルテーム
●着色料:クチナシ色素、食用黄色4号など
●酸化防止剤:エリソルビン酸ナトリウムやビタミンE
●発光剤:亜硝酸ナトリウムや硝酸ナトリウム
●防カビ剤:オルトフェニルフェノールやジフェニル etc…..
《2024年(令和6年)3月1日改正時点では、476品目が指定》
既存食品添加物
長年使用されていた実績をもとに厚生労働省が使用を認めている添加物。
例:●着色料:ウコン
●増粘安定剤:アルギン酸、アマシード
●調味料・強化剤:アルギニン、アラニン
●酵素:アシラーゼ etc…..
《2020年(令和2年)2月26日改正時点では、357品目が指定》
天然香料
動植物から得られる天然物質で、食品に香り付けをする目的で使用されるもの。
例:●バニラ香料、酵母、乳香、ココア、マスタード、黒糖、ハッカ etc…..
《2025年(令和7年)7月時点では、約600品目が収載》
一般飲食添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されているもの。
例:●着色料:赤キャベツ色素、赤ダイコン色素、イカスミ色素、ターメリック、抹茶
●甘味料:アマチャ抽出物、カンゾウ
●製造用剤:セルロース、寒天
●調味料:乳清
●苦味料:ホップ etc…..
《2025年(令和7年)7月時点では、約100品目が指定》
※添加物の物質詳細についてもっと知りたい方は、下記厚生労働省のサイトから閲覧できるので、確認してみてください♪
と、国が指定している食品添加物について基本情報と分類などを紹介しましたが、なんだかわかりづらくなってしまったので、今度はわかりやすく、どのような役割を果たしているのか、みていきましょう。
食品添加物の役割
1、食品の品質を保つ
食品添加物の保存料や酸化防止剤、防カビ剤などの製品は、食品の腐敗や酸化を防いで品質を長く保つ役割があります。そのため、食品ロスの役割もあります。
2、食品の色味と香りを良くする
食品添加物の着色料や発色剤、調味料、甘味料、香料などは、食品の色味や風味を良くするために使用されています。
3、食品を形成しやすくしたり、食感を良くする
食品添加物の膨張剤や乳化剤、安定剤、ゲル化剤などは、豆腐やプリンなど食品の形成を保ったり、独特な食感を出しやすくしています。
4、食品の製造及び加工時に必要なもの
食品添加物のph調整剤、消泡剤、離型剤などは、食品の製造や加工をしやすくするために使用されています。
5、食品の栄養成分を補填する
食品添加物のビタミンやカルシウムなどは、食品の栄養素が足りないときに栄養を補填するために使用されています。
さて、ここまで紹介して皆さん、思っていることは一緒じゃないでしょうか。。。。。
ほとんどの食品に入ってるし、食品に必要不可欠なものでは(汗 )
ほんとそう、わたしもそう思いました(泣)
すべての添加物を抜くという生活は現実的ではないとみなさんお気付きかと思います。では、なぜ添加なしが良いという方が多いのか、、、、食品添加物の注意点もみていきましょう。
食品添加物の注意点
1.アレルギー成分が入っている場合がある
食品添加物には、アレルギー成分の含んだ製品が存在します。特に大豆由来、乳成分由来など。そのため、アレルギーの方は事前に確認をする必要があるため注意が必要です。
2.食べ過ぎによる生活習慣病への影響
食品添加物の中には、食感や味、風味を良くするために使われているものがあります。そのため、ついついおいしくて食べて過ぎてしまうと生活習慣病などのリスクがあるため注意が必要です。
3.摂取量が決められていること
食品添加物は、国により使用してよい限度摂取量が決められています。もし、限度量より多く摂取し続けた場合肝機能低下や発がんリスクなど、人体に影響を及ぼす可能性があります。
4.食品添加物だけでは食品として使用できない
食品添加物は、あくまでも食品の質の向上、安定および栄養のサポートを目的として作られた製品になるため単体での製品提供はできません。
以上が食品添加物の注意点になります。
ここまでみて皆さんはどう感じたでしょうか。
どの注意点も気になるところですが特に注意点3の、『摂取量を超えた場合の人体への影響』がやはり『食品添加物=よくないもの、あぶないもの』になってしまった可能性があります。たしかに、摂取量を毎回把握することもできないため知らないうちに摂取量を超えてカラダに影響が出てしまったら怖いですね。そうならないために、どの食品に多く含まれているのか知っていく必要があると思います。では、どの製品に多く含まれているのか確認をしていきましょう。
食品添加物が多く含む製品
1.コンビニ弁当・惣菜
使用目的: 保存性、色合い、味の安定
使われやすい添加物:保存料(ソルビン酸)、酸化防止剤(ビタミンCなど)、pH調整剤調味料(アミノ酸など)、着色料(赤102、カラメル色素など)
2.ハム・ソーセージ・ベーコンなどの加工肉
使用目的: 発色、保存性、味
使われやすい添加物:発色剤(亜硝酸ナトリウム)、保存料(ソルビン酸カリウム)、結着剤(リン酸塩)、調味料(アミノ酸など)、
3.カップ麺・インスタント食品
使用目的: 味付け、保存性、食感の調整
使われやすい添加物:調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤、乳化剤、増粘剤、安定剤、合成甘味料(スープに含まれることも)
4.お菓子類(スナック菓子、グミ、キャンディなど)
使用目的: 味や見た目の調整、保存性
使われやすい添加物:着色料(タール系:赤102、青1など)、合成甘味料(アスパルテーム、スクラロース)、酸味料、香料、光沢剤
5.清涼飲料水(特にゼロカロリー系)
使用目的: 甘味や酸味、保存
使われやすい添加物:合成甘味料(アスパルテーム、アセスルファムKなど)酸味料、香料、保存料(安息香酸ナトリウム)
6.冷凍食品(フライ・揚げ物・弁当用おかずなど)
使用目的: 冷凍中の品質保持、味、色、食感
使われやすい添加物:増粘剤、安定剤、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、着色料
以上が食品添加物が多く含まれている製品になります。
やはり、一般的に注意すべき食品に食品添加物が多く含まれているようですね。ただ、この情報だけでは食品を購入する際に一瞬で判断するのは難しいです。
じゃあ、どのように注意すればいいの?
食品添加物を摂取しすぎないために注意すべきこと
摂取しすぎると危険な食品添加物を把握しておく
食品添加物はいろんな種類があります。カラダに悪影響が起きる可能性のある製品を把握しておくと意識して摂取を控えることができます。
(例)・亜硝酸ナトリウム→ニトロソアミン(強力な発がん物質)を生成
・タール系合成着色料(赤色2号、黄色4号、青色1号など)→一部にアレルギー反応・多動症(ADHD)との関連が指摘されている
・ソルビン酸カリウム(保存料)→高濃度でDNA損傷や発がん促進作用の可能性が指摘されている
・グルタミン酸ナトリウム(MSG、うま味調味料)→過剰摂取で「中華料理症候群」(頭痛・しびれ・動悸)と呼ばれる症状を起こすことがある。
製品の表示ラベルを確認する
添加物が多い食品は、原材料名の後ろの方にずらっとカタカナや数字が並んでいることが多いです。そのため、製品を購入する時は製品の表示ラベルを確認することをおすすめします。
さいごに・・・
食品添加物は食中毒の防止、品質の向上そして食をおいしくする役割があるということ、国として限度量を定めて人体に影響が出ないよう管理されているのでそんなに警戒する必要はないと思います。ただし、過剰摂取はやはりカラダに危険なため摂取量を気にする必要はあります。今後も食品添加物の役割、注意点を意識しながら上手に使用していきたいですね。
●甘さ控えめ、カラダに優しいシフォンケーキとを販売中(品質・衛生上のため冷凍にて配送 )●
※無添加・保存料/着色料不使用で製造しています。
≪豆腐・チョコレートなどの原材料によって添加物が含まれる場合があります。≫